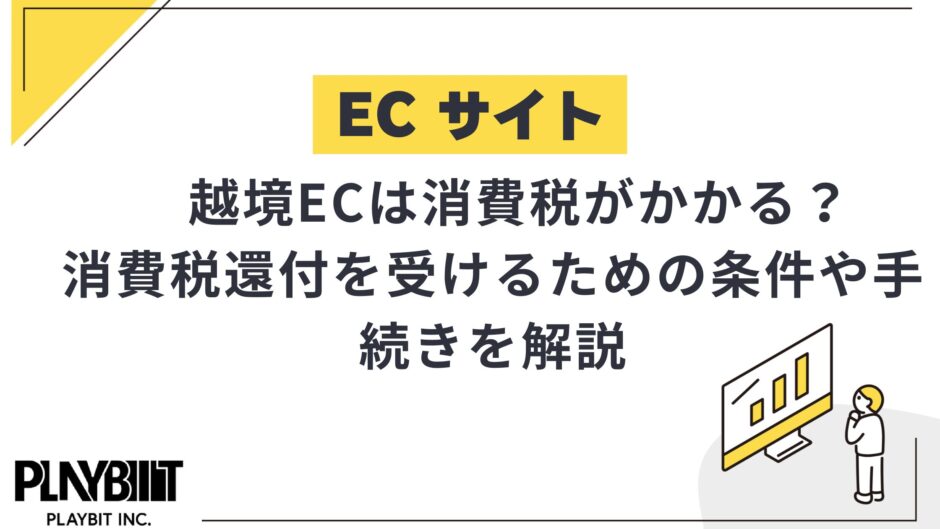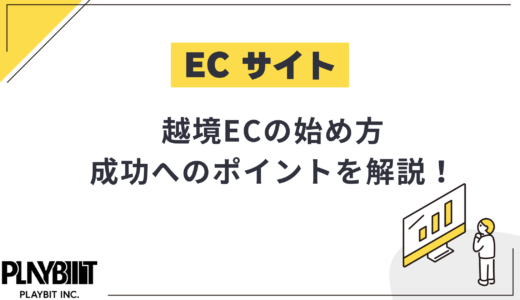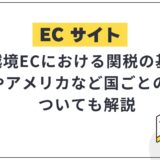*本サイトはアフィリエイトプログラムを利用しています。
越境ECの運営には、税務の知識が必要不可欠です。特に消費税は、税金の還付を受けられる可能性があるなどメリットが大きいため、ぜひ理解しておきたいポイントです。
しかし、多くの事業者が消費税のルールや還付手続きについて十分に理解できておらず、損をしているケースも多数あります。
本記事では、越境ECにおける消費税の基本から、還付を受けるための条件や手順、注意点までを詳しく解説します。税金で損をしたくないEC事業者は、本記事で消費税に関する正しい知識を身につけましょう。
越境ECでは消費税はかからない

消費税は国内での販売にかかる税金のため、消費者が国外にいる越境ECではかかりません。商品が国外に輸出される取引では「輸出免税」という制度が適用されるからです。
ただし、輸出免税の適用を受けるには、商品の輸出を証明できる書類が必要です。証明書類には「輸出許可証」や、特定の事項が記載された「日本郵便による発送伝票等の控え」などが利用できます。
でECサイト構築・運用支援-Shopifyの作成・制作、運用代行.jpg)
越境ECの消費税還付とは?
消費税還付とは、本来支払う必要がなかった消費税を払っていた場合、後から返金してもらえる制度です。
越境ECでは、消費税を支払う必要はありません。しかし、実際には商品を販売する前の、日本国内での仕入れや、発送、輸出業務で消費税を払っている場合が多くあります。これらの消費税は、本来は支払う必要のないものです。一定の条件を満たし、還付申請すれば、事業者は負担した消費税を取り戻すことができます。
越境ECで消費税還付を受けるための3つの条件
越境ECで消費税還付を受けるには、3つの条件を満たす必要があります。以降で、3つの条件について詳しく解説します。
1.課税事業者であること
まず、消費税還付を受けるためには、「課税事業者」でなければなりません。課税事業者とは、基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者です。新設法人の場合は資本金が1,000万円以上なら、原則課税事業者として扱われます。
また、課税売上高が1,000万円未満でも、「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出すれば、課税事業者になることができます。
2.「原則課税」を選択していること
次に、還付を受けるには、消費税の計算方式で「原則課税方式」を選択している必要があります。原則課税方式とは「売り上げに含まれる消費税額」から「仕入れや経費でかかった消費税額」を差し引いた金額を、消費税として納税する計算方式です。
これに対し「売り上げに含まれる消費税額」に「業種ごとのみなし仕入率」を掛け合わせて消費税額を産出する方式を、簡易課税方式と呼びます。簡易課税方式は中小規模の事業者向けに用意された制度であり、事務負担が少ないというメリットがあります。しかし、消費税の還付は受けられません。
越境ECで消費税の還付を受けたい場合は、必ず原則課税方式を選択しましょう。
3.必要書類を提出していること
最後に、消費税還付を受けるためには、必要書類を提出しなければなりません。必要な書類は「消費税及び地方消費税確定申告書」「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書」「消費税の還付申告に関する明細書」です。
他にも国外への商品の輸出を証明するために、輸出許可証の提出が求められたり、すでに消費税を支払っていることを証明するために、仕入れの納品書や領収書の提出が求められたりする可能性もあります。
越境ECで消費税還付を受け取る手順

以降では、消費税還付を受けるための手順を、具体的に解説します。
手順1.消費税の課税事業者になる
まず、消費税還付を受けるためには「課税事業者」になる手続きをしましょう。基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば、自動的に消費税課税事業者に登録されます。課税売上高が1,000万円未満で、課税事業者になりたい場合は、前述の「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出しましょう。
免税事業者が課税事業者になる場合、適用を受けたい課税期間の初日の前日(事業年度の最終日)までに、消費税課税事業者選択届出書を提出しなければなりません。
例えば、事業年度が4月1日~3月31日で、次期の4月1日から課税事業者になりたい場合は、今期の3月31日までに消費税課税事業者選択届出書を提出する必要があります。
手順2: 消費税の課税方式で「原則課税方式」を選択する
次に、消費税の課税方式として「原則課税方式」を選択します。課税方式の選択は、消費税課税事業者選択届出書の提出と併せて行いましょう。
現在、簡易課税方式を選択しており、原則課税方式に切り替える場合は、簡易課税の適用をやめようとする課税期間初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しなければなりません。
手順3: 消費税の確定申告を行う
最後に、消費税の確定申告を行いましょう。消費税の還付を受けるためには、所得税の確定申告とは別に、消費税の確定申告を行う必要があります。「消費税及び地方消費税確定申告書」「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書」「消費税の還付申告に関する明細書」の3つの書類を、申告期限までに税務署に提出しましょう。
申告期限は、法人の場合は事業年度終了日の翌日から2カ月以内で、個人事業主の場合は翌年3月末までです。なお、提出方法は、税務署への持ち込みや郵送以外にe-Taxも選択できます。
越境ECで消費税還付を受ける際の注意点
消費税還付は越境EC事業者にとって大きなメリットがありますが、還付を受ける際にはいくつかの注意点もあります。以降では、特に重要な3つの注意点について解説します。
2年間は免税事業者への変更ができない
消費税還付を受けるには、課税事業者になることが必須の条件ですが、一度課税事業者を選択した場合、その後2年間は免税事業者に変更できません。たとえ、その後売り上げが減少しても、課税事業者になってから2年間は、消費税の納税義務が発生します。
消費税還付分のメリットよりも、消費税負担分のデメリットのほうが大きくなる可能性もあるため、今後の事業の成長を加味しながら慎重に判断しましょう。
還付金はすぐに支払われない
消費税還付を申請しても、還付金がすぐに支払われるわけではありません。申告書を提出してから還付金が振り込まれるまでには、通常1カ月から1カ月半程度の時間がかかります。
また、税務署の審査によってはさらに時間がかかるケースもあるため、消費税還付分を運転資金に充てたい場合は、できるだけ早く申請しましょう。
e-Taxで申請すると2~3週間程度で還付金が振り込まれるので、できるだけ早く還付金を受け取りたい場合は、e-Taxでの申請をおすすめします。
各書類は保管義務がある
消費税還付を受ける際に提出する書類や関連資料は、7年間の保管義務があります。税務調査の際に確認される可能性もあるので、提出を求められたらすぐに出せるよう整理し、厳重に保管しましょう。
必要書類が適切に保管されていないと、消費税が還付されるまでに時間がかかったり、最悪の場合還付自体が取り消されたりしてしまう可能性もあります。
越境ECの消費税対策を万全に!
本記事では、越境ECにおける消費税の還付について、基本的な仕組みや還付を受けるための手順、注意点などを解説しました。
越境ECを運営する事業者にとって、消費税還付は資金負担を軽減できる重要な制度です。しかし、還付を受けるためにはいくつかの条件や必要書類があります。また、一度課税事業者になると、その後2年間は免税事業者に戻れなかったり、還付までにはある程度の時間がかかったりすることも忘れてはいけません。
本記事を参考に、越境ECの消費税についてしっかりと理解し、事業の成長に活かしましょう。
越境ECの始め方は以下の記事を参考にしてください。
おすすめShopifyアプリ